![]()
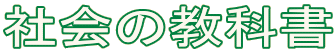
「『社会』を考えることって、『自分』が生き生きできることにもつながってるんだ。」
教室の中でそう実感できたら、授業中、窓の外の風景を見ながら、薄ぼんやりと自分のことを考えていなかったかもしれない(それはそれとして、やっぱりぼんやりとはしていたのかもしれない)。
いずれにしても、ここに掲載する文章は、竹田青嗣さん、西さんが、高校生の教科書のために書き下ろした文章の一部です。教科書の刊行は残念ながら実現しませんでしたが、考えることの喜びに出会う一冊、考えることの原点を確認できる一冊になったんだろうな、と思います。そういう、本棚の一端にいつまでも置いておきたい本が、教科書であってもよかったのに。![]()
【世界の意味】
優れた民族学者、M・エリアーデ(*1)はこう言っている。神話とは「世界の意味を教えるものだ」、と。これはどういうことだろうか。
たとえば、ユダヤ教の神話では、神は男女を創ったあと楽園に住まわせるが、二人は知恵の木の実を食べて堕落し、楽園を追放され、以後人間は労働と出産と死の苦しみを負うようになる、とされている。ここに、世界はなぜ存在するのか、人間はなぜまた何のために生きて苦しむのか、といった問いに対する一つの答えが、物語の形で答えられていることが分かるだろう。つまり、人間は大昔から、《生の意味》ということについて何らかの答えを見つけようとしていたのである。
この生と世界への問いは、世界中どこでも、まず宗教的な神話という形をとり、つぎに哲学的思考の形をとって現われてきた。哲学も宗教も人間についての思想だが、哲学は物語を使わないで、抽象概念を論理的に使って世界を説明するという特徴をもっている。このことで哲学は、人間についての思想を、特定の文化や民族を越えて、いわばどんな人間でも参加できる開かれた《言語ゲーム》としたといえる。
しかし、宗教は宗教でまた大事な特質をもっていた。その根にあるのは、ドストエフスキーのことばを使えば、人々の、自分たちの現実生活を超えたところに「はるかに優れたものが何かあるに相違ない」(*2)と考えてそれに憧れるような心性、だからである。
さて、宗教や哲学思想の歴史を見てみると、時代時代で、その問題の形が異なっていることが分かる。たとえば、古代ギリシャでは、ポリス社会における人間の「美徳」とは何か、ということが中心問題だった。中世ヨーロッパでは、「真の信仰」とはいかなるものか、が大問題となる。このように、時代によって問題の形は大きく変わるのだが、それらが結局人間の「生の意味」への問いから発していることは変わらない。そして、近代に入ると宗教思想はやや後退し、近代思想が人間のモラルの問題、社会の問題などをいっせいに開花させることになる。
【思想の原理】
ところで、人間はなぜ、宗教や哲学という形で思考をつづけてきたのだろうか。その理由は、一見深遠かつ難解なものに思える。だがほんとうはとてもシンプルである。人間が、生につきまとう不安や苦痛をできるだけ和らげ、また可能なかぎり深く楽しく生きるためである。人間は誰でも生きて問題にぶつかり、悩む。このとき、深くよく考えれば、自分や自分の関係を改善しより豊かに生きられる可能性がいつでもある。宗教や哲学は、要するに、そのためのよい知恵、考え方の方法なのである。
人間は、《動物と違って社会を営んでいる》。したがって人間の世界はいわば「関係」の世界である。だが、その「関係」の全体的な像は誰にとっても十分には見えない。だからこそ、それをたしかに理解できれば、そのことは必ずわれわれの生きることに役立つ。それが思想ということの「原理」だ。
宗教や哲学の思考は、かつてはいわゆる「倫理」や「道徳」というすこしいかめしい形をとることが多かった。その理由は、生活の条件が十分に豊かでない場面では、人間はまず、欲望をうまく抑えたりなだめたりする必要があるからだ。しかし、もちろんそれだけが思想の役割ではない。人々が互いに調和的に共存しつつ、同時に個々人が深く豊かな生を生きるための優れた知恵を創りだすこと、思想は、すこしづつそのような本来の課題を切り開きつつあるといえる。
【思想の歴史を学ぶこと】
人類は思想や哲学の長い歴史を残してきた。ふつうの人が受け取るにはかなり難しい面もある。しかし、もしうまく日常の言葉におき直すような形で理解できたら、それはわれわれにとってとても貴重な知恵の泉になる。人類が残したこの知恵は、拝んではいけない。つねに、自分たちの時代に合わせる形で理解し直さないと宝の持ち腐れだ。そしてその仕事は、いつも必ず新しい若い世代の役割なのだ。
ギリシャの哲人ヘラクレイトスに、「たたかいは万物の王である」という有名なことばがある。たたかいだけが世界の秩序を決めるというのだ。だが、たたかいには必ず悲惨な支配と被支配の関係がともなう。人間社会は、ながく、民族や宗教どうしの間のたたかいや支配の関係を繰り返してきたし、いまもそれは完全になくなったわけではない。それがまだ人間社会の過酷な現実なのである。
どのように考えれば、人間世界から悲惨な戦争や支配の関係をなくしていけるのか。また、差別や制度上の不合理などを少しづつ改善してゆけるのか。人類は、この人間社会全体にかかわる問題をずっと考え続けてきた。わたしたちもまた、つねにこの問題に関心を払い、配慮すべきなのは、ある意味で当然のことだ。
が、しかし、じっさいにはそれは言うはやさしで、なかなか簡単なことではない。まずこの、人類全体がよくなるために何が必要なのか、どう考えればいいのかといった問題は、ふつうの生活からとても「遠い問題」だ。またそこには、いろいろ複雑な問題がからんでいて、そうとう専門的な知識を必要とする。だから、じっさいは、そういうことは、訓練をつんだ専門家が引き受けるべき問題ではないか、という見方もあるかも知れない。
しかし、つぎのような考え方もある。
【関係を大事にすること】
「世界の永遠平和」という可能性をはじめて提唱したカントは、こんなことを言っている。人間の「理性」には独特の本性がある。人間の理性は、ひとつのことがらを考えはじめると、どうしてもその「全体」や「完全」な像までいきつこうとする性質がある、というのである。これはとても面白い考えだ。
だれもまず、自分の「生きること」に配慮している。そのために、自分をとりまくいちばん近い人間たちを大事にするだろう。そして、自分をとりまく「人間関係」自体を大事にしようとする気持ちがあれば、どうしても、その人間関係を支えている外側の諸条件、つまり、地域とか、社会とか、国とか、さらに、世界の国どうしの関係や状態が、大なり小なり気になってくるだろう。この「気になってくる」という心の動きが重要だ。
つまり、人間はだれでも、自分の「生きること」を大切に思い、自分の「関係」をよくしようとする気持ちが強くなるほど、その回りのさまざまな条件をできるだけよい状態にしたいと思う、内的な理由をもっているのだ。
たとえば、自分の家で両親が不仲だったり、自分の学校がひどく荒れていると、気持ちがすさみ、いろんなことがどうでもよくなってくる。自分をとりまく世界の状態が悪いのに、これをどうにもできないという感覚は、人間の生きる元気や希望を腐らせる。ニヒリズムとはそういうことだ。しかし、こうすれば少しずつでも状態がよくなっていく、という考え方や「可能性」があれば、つらい状態にも耐えることができるし、わたしたちの生に希望が現われる。それが人間の本性なのである。
友達、家族、学校、会社、地域、自分たちの政府、そして世界の国々の関係。それらはわたしたちをとりまいている「生」の条件だが、徐々にでもそれを改善していける「可能性」のイメージがあるということは、いつでもわたしたちの「生きること」を元気づける。このようなすじみちが、世界のいろんな場所で、いろんな人間が、世界の全体や人間の未来のあり方を考えることの普遍的な動機であり、理由なのである。
【自分と世界を理解するために】
人類の福祉や世界の未来について考えること、それは一見、ふつうの生活からひどく「遠い」ことのように思えるかも知れない。しかしそれは、「みんなもっと世の中のことを考えるべきだ」という優等生の意見ではなくて、もともと、自分の生き方や人間関係を大事にする、という起点からはじまるものだ。この起点がうまく立たないと、わたしたちに、「人類の福祉」ということを考えるしっかりした動機も元気も出てこない。みんながますますバラバラになる。
人類の未来なんてことまで自分は知らないよ、と言いたい人も中にはいるだろう。でも、もしかするとその人は、何らかの理由で、自分の生や関係に対する思いが傷ついているのかも知れない。人間であるかぎり世界や人類全体の問題について配慮すべきだ、と考える必要はない。むしろ、人間は、自分の「生きること」への思いをうまく育てることができれば、自然に回りの社会や世界の全体を気遣うような存在だと考えればいい。
「人類の福祉」についての全体的なイメージを育て、それを仲間とともにゆっくり考えていくことは、自分の生き方をよく理解し、これを刷新していくための一つの大事な道すじなのである。
【国家はつくりもの】
西欧の中世では、貴族と農奴といった身分制度は、神が定めたものであって変更不可能なものと考えられていた。近代になってはじめて、国家もそこでの秩序も、人びとが幸福に生きるためにみずからつくりあげたものであり、だからこそ変更可能であるという思想が生まれてくる。国家のために人間があるのではなく人間のために国家がある、とする点でも、同一民族による国家ではなく、血縁や文化と関わりない対等な人間どうしが国家をつくるとする点でも、この【社会契約説】は人類の歴史のうえで画期的な思想であるといえる。
【ホッブズ】
その創始者はイギリスのホッブズ(T.Hobbes,1588-1679)である。彼はピューリタン革命のはげしい内乱の時代に『リヴァイアサン』を著して、社会秩序の必要性を訴えようとした。ホッブズは、人間は【自己保存】の衝動をもっており、名誉・権力・富などを求めて互いにせめぎ合う存在であると考えた。だから、法もそれを守らせるための権力も存在しない【自然状態】のなかにあるかぎり、人は必ず「【万人の万人に対する闘争】」を引き起こし、絶えざる死の危険にさらされることになる。そうした状態を逃れるために、一人の個人ないしは合議体を「主権者」としてその命令に従うことにする、という契約を人びとは取り結び、こうして国家をつくりあげたと述べた。この思想は、国家を神から与えられた秩序と考える旧来のキリスト教的な見方を捨て、それを個々人の自己保存と共存のためのものとして新たに定義した点で、まさに画期的なものであった。しかし秩序の安定を第一とするホッブズは、主権者の権力を絶対のものとして人びとの反抗を認めようとせず、それは後に厳しく批判されることになる。
【ロック】
名誉革命が成立して平和が達成された時代に、ロック(J.Locke,1632-1704)は『市民政府論』を著して、人間の基本的権利を明確に定め、その権利を守ることこそが国家の役割であるとした。ロックはまず、人間には「他人の生命・健康・自由及び財産を犯してはならない」という【自然法】が神によって与えられている(この四項目はだれもがもつ権利として、【自然権】とも呼ばれる)と述べる。だから自然状態においても人びとはそれなりに平和に共存しているが、ある行為が自然法に違反しているかどうかの判断が人びとの間で対立したとき、これを解決する手段がない。そこで裁定を下す裁判官とそれを守らせる共通の権力が必要となり、そのために人びとは同意して一つの国家をつくることになる。ロックは、議会や政府は権利の保護のためのものであるから、その目的に反した場合には人びとは議会や政府を変更できるとして、明確に【抵抗権】を認めた。基本的な権利の設定と抵抗権の思想は、民主的な国家のあり方を確立するうえで大きな功績であり、現代の多くの国家に受けつがれている。しかし権利を神が与えたものと説明したことは、権利を神聖不可侵なものとして印象づけるには効果的であったとしても、権利も他の法と同じく人びとのあいだの取り決めであるとする、社会契約説本来の見方を弱めた面がある。
【ルソー】
十八世紀のジュネーヴに生まれたルソー(J.J.Rousseau,1712-78)は、「自分自身の主人であること」、つまり、みずからの意志に従って人生を営む自由をきわめて重要な価値と考えた。この自由が損なわれることのない社会的結合のあり方について追究したものが『社会契約論』であり、後のフランス革命に大きな影響を与えた。ルソーは、一人の力では自己保存するのが難しくなり力を合わせる必要が生じたときに、人びとは契約して政治体(国家)をつくるという。この国家を動かすためには法が必要となるが、主権者は人民であり、人民集会において法案が審議され、最終的には多数決によって制定されるとして、【民主主義】の思想を明確に打ち出した(*)。しかしルソーは、こうした手続きだけで自由な社会が可能になるとは考えなかった。もし私が私の一族だけが得をする法案に票を投じてそれが成立するならば、損をする残りの人びとはその法を強制されることになり、だれもが自由な社会は実現しない。だれもがそれを欲する(意志する)もの、つまりだれにとっても得になるという意味で真に共通の利益であるものが法となるときにだけ、人びとは納得してそれに従うことができる。この意味で、法は【一般意志】(成員だれもが欲すること)に基づかねばならない、とルソーはいう。彼はまた、ロックのいうような自然法・自然権を否定して、法や権利はすべて一般意志にもとづく取り決めであるとした。法や権利の内容のよし・あしの基準を一般意志というかたちで定めたことは、きわめて大きなルソーの功績であるといえる。
(註)
*ルソーは、議会制民主主義ではなく直接民主主義こそほんらいの民主主義であるとした。
![]()
善悪を判断するための絶対にただしい基準、というようなものがはたして存在するだろうか。私たちの多くがこのことを疑うにちがいない。しかし、善悪の判断基準は確かに存在しているのであって、それは明確な形で示すことができると考えた人がいる。十八世紀末に活躍したドイツの哲学者、カント(I.Kant 1724-1804)である。
【自律】
カントがまず強調したのは、善悪を判断する主体はあくまでも自分自身でなければならない、ということだった。教会や領主が善とすることに従うこと(他から律せられる=他律)には、道徳的な価値はまったくない。その行為が正しいかどうかをみずから洞察して行為すること(自分で自分を律する=自律)にこそ道徳的価値がある、とカントははっきりと述べた。権威に盲目的に従う姿勢を批判して、主体的な判断に価値を認めるこの思想は、教会と領主が強い権力をもっていた当時のドイツにあって、きわめて新鮮な自由の息吹きを感じさせるものだった。
【定言命法】
しかし一人一人が主体的に判断するということになれば、結局のところ、善悪は相対的なものになってしまいそうである。しかしカントはそう考えなかった。人が自分のなかの理性の声に耳をすましてみれば、それはつねに一つのことを命じているからである。すなわち、〈あなたが従おうとするルールは、ほんとうにだれもがそれを採用できるような一般性をもっているか、確かめてみよ。そして一般性をもっているときにだけ、そのルールに従って行為せよ。(*)〉この理性の命令は【定言命法】と呼ばれるが、これについてカントは次のような具体例を挙げて説明している。金に困っている人が、期限内に返せないと知りつつ嘘をついて借金しようとしているとしよう。彼のルールは「困っているときには嘘の約束も許される」ということになるが、このルールを皆が採用したとすれば、約束は守られるかどうかわからなくなり、結局は約束という行為じたいが成り立たなくなる。だから、嘘の約束は許されないことになる。このように、定言命法に従うならば善悪の判断はただしく一つに決定されるとカントは主張したのだった。
しかし、定言命法の語ることにピンとこない人もいるかもしれない。じっさいに私たちが「これはいいことだ」とか「これはやってもいいだろう」と判断している場合を思い出してみよう。すると、暗黙のうちに「だれだって自分と同じように考えるのではないか」という思いが伴っているはずである(自分なりに確かめてみてほしい)。だとすれば、定言命法は「そのルールがほんとうに一般的なものかどうかを、きちんと検証してみるべきだ」と命じていることになり、それほど特別なことを語っているのでないことがわかるだろう。
カントはさらに、ルールが万人に通用することを求める定言命法のなかには、おのずと【人間性の尊重】ということが含まれていると考えた。それをはっきりと言葉にすれば、「あなた自身の人格、およびすべての他人の人格のうちにある人間性を、つねに同時に目的として取り扱い、けっしてたんに手段としてのみ取り扱わないように行為せよ(『道徳形而上学の基礎づけ』)」という命法となる。つまりカントは、道徳の本質は人間性の尊重にあると考えたのである。これもまた、大きな説得力をもつ思想であった。
【カントへの批判】
しかしカントの道徳説は高い評価と同時に、大きな批判にもさらされることになった。一つはカントが道徳と快楽とを完全に切り離して対立させた点である。カントは人間を、快楽を求める動物的な面と、善をなそうとする理性の面とを合わせ持つ二重の存在であると捉え、快楽に負けずにつねに善をなそうと努めるところに人間としての尊厳があるとした。そこには、神への信仰に代わる新たな生の目標として、道徳的な生き方をうち立てようとする意図がみられる。しかし喜びと善とを完全に対立させる点を不自然と感じる人も多くあった。第二に、善悪を自分のなかの理性によって確実に判断できるとする点を批判する人もあった。たとえば後のヘーゲルは、善悪は自分の内側だけでは十分に確かめることのできないものであり、他者との具体的な関係のなかで相互に確かめあうことによってはっきりしてくるものだと主張している。
しかしカントが道徳的判断の主体性を重んじたこと、判断が真に一般的かどうかを検証すべきだと主張したこと、そして特定の民族や国家の枠を超えて人間性そのものの尊重を求めたことは、やはり重要な功績といわねばならないだろう。
(註)
*この理性の声は、仮言的な命法(〜でありたいなら…せよ)ではなく、「端的に…をせよ」と命ずるものであるから、定言命法と呼ばれる。カント自身の表現は以下のとおり。「あなたの格率[=あなたの個人的なルール]が一般的法則となることを、それによってあなたが同時に意志しうるような、そういう格率に従ってのみ行為せよ」(『道徳形而上学の基礎づけ』)
![]()
![]()
![]()
近代になると、ロックが権利の尊重を訴え、カントが道徳における自律を説き、ルソーの説いた民主主義がフランス革命として実現されてくる。ドイツの哲学者ヘーゲル(G.W.F.Hegel,1770-1831)は、こうした歴史の趨勢を、人類がしだいに自由を実現していく過程であると考えた。
【自由】
人間は「自分」を意識する存在である。そこには、自分に関わることは自分で決定したいという【自律】(自己決定)への要求と、自分を他者から価値あるものとして認められたいという【承認】への要求とが含まれている、とヘーゲルは考えた。ふつう自由といわれるときには自律だけがイメージされるが、ヘーゲルは他者からの承認ということも具体的な自由にとって欠かせないと考えたのである。
人は承認を獲得するためにさまざまな試みを行う。他者と争って自分のほうが力が強いことを示そうすることもある。逆にこうした他者との争いを嫌って自分のなかに閉じこもろうとすることもある。しかしこうすることでは真の自由は得られないとヘーゲルはいう。ではどうすることで得られるのだろうか。
何かの作品(絵や料理や実用品)を作ってみるとする。最初はただ作るだけでも面白いが、だんだんそれだけでは満足できなくなる。他人の作品を見ると、自分の作品に足りない点があることがわかってくるからだ。そこで、もっと優れた作品、つまり自分も他人もその価値を認めるような作品をつくりたいという気持ちが目覚めてくる。人は、ほんとうに価値ある作品や仕事をめざしているという感覚をもち、じっさいに他者からも「君はほんとうに価値あることをやっている」と承認されるときに、自由を実感できるとヘーゲルは述べた。
【近代】
個人が試行錯誤しながら自由を求めていくように、人類全体の歴史も一歩一歩自由を実現していく過程としてみることができるとヘーゲルは考えたが、その観点からみたとき、近代は個人の自律への要求がはっきりと現れてくる時代だといえる。近代以前の共同体においては、人は神への信仰と共同体の伝統的な掟のなかで生きており、そうした生き方に疑いをもつことがない。ところが近代になると、自分自身の判断と意志に従って生きようとする個人が登場してくる。この個人は、常識やしきたりについても無批判に受け入れることをよしとせず、「これはだれもが納得しうる一般性をもつか」ということを自分で検討し、納得したことにだけ従おうとする。こうした自律を求める姿勢は、自由な議論の場である学問や、民主主義の政治体制という仕方で、制度的にも実現されていくことになる。しかし他方で、共同体から切り離された個人は、共同体の掟や神への信仰のような、生の目的をあらかじめ与えられていないため、生の意味の不安を抱え持つことにもなりやすい。上でふれたように、ヘーゲルは具体的な自由のためには他者からの承認が必要であることを強調し、一人ひとりが具体的な他者関係のなかで「どういうことがほんとうに一般的な価値をもつのか」をみずから確かめ、それを自分自身の目的とすることが大切であると述べた。
【家族・市民社会・国家】
ヘーゲルは他方で、具体的な自由は個人の態度の取り方だけで獲得できるものではなく、個人を社会制度が支えることによってはじめて可能になるという考えをもっていた。人間の生活の領域を、彼は大きく三つの制度に区分している。一つは【家族】であり、ここでは男女は一体となって愛しあい、子どもを育てる。次が【市民社会】と呼ばれる経済の領域であり、一人ひとりが自由に職業を選び自由に私的利益を追求し、一人前の職業人として認められることで「自主独立の誇り」を持つことができる。しかし市民社会は、放置すれば極端な貧富の差が生まれ、努力しても報いられないような状態になる。そこで経済政策も含めて社会全体のあり方を配慮する必要が出てくるが、この役割を果たすのが【国家】という政治制度である。国家において、人は自分や家族の利益だけでなく、社会全体について配慮することになる。家族における愛、市民社会における自己実現、国家における社会全体への配慮、これらすべてが一体となって具体的な自由は可能になるとした。
ヘーゲルはしかし、当時のドイツの事情を考慮したためか、民主制でなく立憲君主制を本来の政体であるとし、さらに国連のような国家の上位にたつ政治制度を認めようとせず、戦争のさい国のために命を危険にさらすことを国民の当然の義務とした。このため後世から、国家主義者であるという非難を浴びることにもなった。